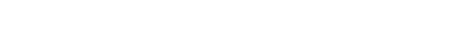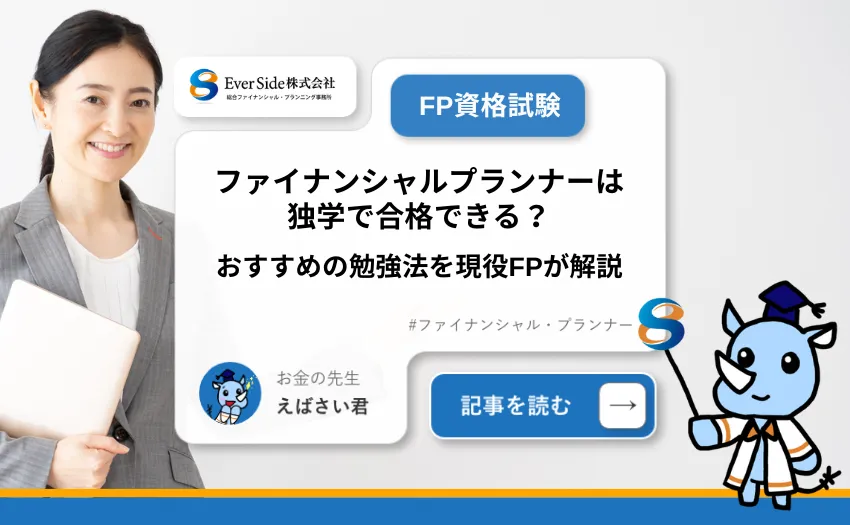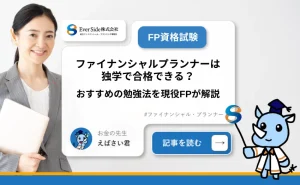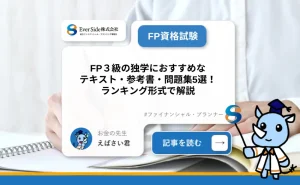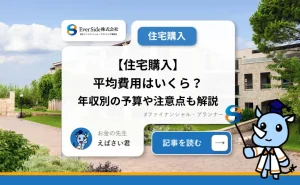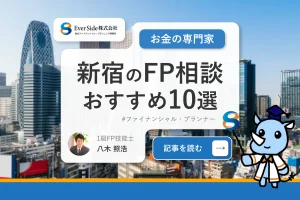FP資格は、金融や不動産などお金にまつわる知識や知見を有する人として認められる国家資格の1つです。
お金に関する資格としては認知度が高く、根強い人気があります。転職やキャリアアップにも有利な資格として認知されているFP資格は、独学で合格できるのでしょうか。
そこで今回は、FPの試験範囲や合格率を解説しながら、効果的な勉強方法について解説します。
お金に関する質問やお困りごとがありましたら、ぜひ「えばさい君の相談室」の無料相談をご利用ください。総合ファイナンシャル・プランニング事務所「EverSide株式会社」では、サービス詳細やお客様の声もご紹介しています。併せてご覧ください。
\ まずは無料でFP相談をしてみる /
本コンテンツはえばさい君が独自の基準に基づき制作していますが、紹介先から送客手数料を受領しています。
FP技能検定の概要
FP資格の勉強を始める前に、試験範囲や試験方式を把握して、適切な対策ができるようにしておきましょう。
FP資格は、1級、2級、3級に分類されます。それぞれの受験資格は、以下の通りです。
- FP3級:FP業務に従事している者または従事しようとしている者
- FP2級:3級FP技能検定の合格者、受検申請時点で、FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者、受検申請時点で、日本FP協会認定のAFP認定研修を修了している者、金融渉外技能審査3級の合格者
- FP1級:日本FP協会認定のCFP認定者、日本FP協会のCFP資格審査試験の全ての課目に合格したが認定されていない者、金融財政事情研究会実施の1級FP技能検定学科試験の一部合格者、1級FP技能検定合格者、金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者
FP3級の受験資格は、実際に業務に従事しているかは問われません。
FP2級とFP1級は、実務経験や特定の資格を保有しておく必要があります。では、試験範囲や合格率、試験方式について確認しましょう。
FP技能検定の試験範囲
FP技能検定は、お金に関する幅広い知識が出題されます。FPの試験は、学科試験と実技試験に分かれます。学科試験は、以下のジャンルから出題されます。
- ライフプランニング・リタイアメントプランニング:社会保険や年金など
- 金融資産運用設計:投資信託や株式投資など
- 不動産運用設計:不動産に関する法令上の規制など
- リスクと保険:生命保険屋損害保険など
- タックスプランニング:税制や控除の仕組みなど
- 相続・事業承継設計:相続や贈与に関する対策など
実技試験は、資産設計提案業務から出題されます。
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- ファイナンシャル・プランニングのプロセス
- 顧客のファイナンス状況の分析と評価
問題の難易度は、3級から2級、2級から1級になるにつれて難しくなります。
FP技能検定の試験方式
FP技能検定は、マークシート方式と記述式に分かれます。
基本的に、学科試験はFP1級の応用編を除き、すべてマークシート方式です。マークシートで試験を実施するため、対策が立てやすいでしょう。
一方、実技試験は3級FPはマークシート形式ですが、2級と1級の試験は記述式です。そのため、問題に対する理解はもちろん計算方法についても理解しておく必要があります。
FP技能検定の合格率
FP技能検定の合格率は、以下の通りです。
- FP3級(2024年10月~2025年2月):学科85.4% 実技85.6%
- FP2級(2025年1月):学科44.4% 実技48.8%
- FP1級(2025年1月):学科16.81% 実技82.4%
学科試験でみると、FP3級は85.4%と高い合格率となっています。2級FPの合格率は44.4%と、50%を下回り、1級FPは16.81%と非常に低い合格率でした。
FPは独学で合格できる?
結論としては、FPは独学で合格できる資格です。
独学で合格するために、適切な試験対策と勉強時間をどのように確保すべきか確認しましょう。
出題範囲の対策
FP試験は、出題範囲をどのように勉強するかを確認しましょう。
金融資産運用設計
金融資産運用設計は、経済指標や金融政策をはじめ、損益計算や税制といった幅広い金融面の知識が問われます。
マニアックな問題も多いので、投資や経済に関する知識や知見が求められます。
基本的な対策は、過去問を解きながら国内外の金融政策や経済の動向をチェックしておく必要があるでしょう。
不動産運用設計
不動産運用設計は、基本的な不動産売買の知識や法令に関する知識が出題されます。
不動産の売買で遵守する法律や制限を理解して、過去問レベルの問題が解けるようにインプットとアウトプットを繰り返しましょう。
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
社会保険やキャッシュフロー表の作成など、FPの実務的な知識が理解できているかが求められる分野です。
基本知識の理解をはじめ、表の作成ができるようにアウトプットできるかが大切になります。
リスクと保険
生命保険をはじめ、損害保険についての幅広い知識が問われます。
6科目では取り組みやすい分野の問題です。得点源にできるよう、基本的な用語だけでなく過去問で要点を押さえながら理解しましょう。
タックスプランニング
法人税や所得税といった、税についての計算や手続きについて複雑な問題が出題されます。
また、財務諸表や法人および個人の基本的な税金の仕組みも問われ、非常に学習する範囲が広いため、苦手分野になりやすいです。
過去問を繰り返し活用して、理解を深めてください。
相続・事業承継設計
相続・事業承継は、相続の対策や解決方法に関する問題が出題されます。
基本的な相続や贈与にかかる税の仕組みを理解して、計算や申告など手続きにまつわる知識を押さえておきましょう。
過去問の活用方法
FP試験の対策には、過去問の活用が重要なポイントとなります。
問題集を解くことで、どのような問題が出題されているのか、問題を解くための考え方などを把握します。問題集を解いてアウトプットしながら、テキストでインプットを繰り返すことで知識が定着しやすいです。
FP試験は、過去に出題された問題を流用するケースが多いため、過去問を理解できるまで解き続けることが大切になるでしょう。
実際に出題された過去問は、公式ホームページからダウンロードできるため、活用してください。
実技試験対策
実技試験は、計算問題が出題されるなど問題のパターンや計算式の活用と深い知識が求められます。過去問でどのような問題が出題されているか確認しながら、解答のパターンを理解しましょう。
また、実技試験は学科試験に比べて試験時間が短いので、試験時間内に問題を解けるように慣れておく必要があります。
FP資格を取得するメリット
FP資格を取得すると、さまざまなメリットがあります。
- 独立・起業:FPとして独立した仕事のほか、起業にも役立つ
- キャリアアップ:金融業界や不動産業界で強みが発揮できる
- 家計の見直し:将来の資産形成やキャッシュフローの問題点を見直せる
特にビジネスの場面では、顧客との相談で信頼してもらいやすいです。
保険会社や不動産会社、銀行、士業で活躍する際には、FP資格は活かしやすいでしょう。就職活動や転職にFP資格を役立てるには、2級以上の取得が望ましいです。
3級を取得後、すぐに2級資格をチャレンジして最短で取得すると良いでしょう。
まとめ
FP資格は、これからのキャリアアップや家計の見直しに役立つ人気資格です。
独学でも合格できる資格なので、お金をかけずに資格を取得することもできるでしょう。しかし、試験に合格するには適切な対策と勉強時間の確保が必要になります。
特に、2級FPより上級の資格は合格率が低くなるので、深い知識の定着が必要です。過去問を活用しながら、インプットとアウトプットを繰り返し知識を定着させましょう。
また、実技試験は記述式になっている問題もあるので、計算方法や問題の考え方も身につける必要があります。
\ まずは無料でFP相談をしてみる /

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大手保険代理店で9年間、主に個人のライフプランニングを通した顧客の相談を行う。1500件を超えるこれまでの相談経験から、顧客の課題や悩みに幅広く寄り添える独立系のFPを志し活動している。FPとして顧客の相談を行う一方、3つの金融メディアにて社会保障制度や奨学金制度、家計をテーマにした執筆活動も並行して活動中。